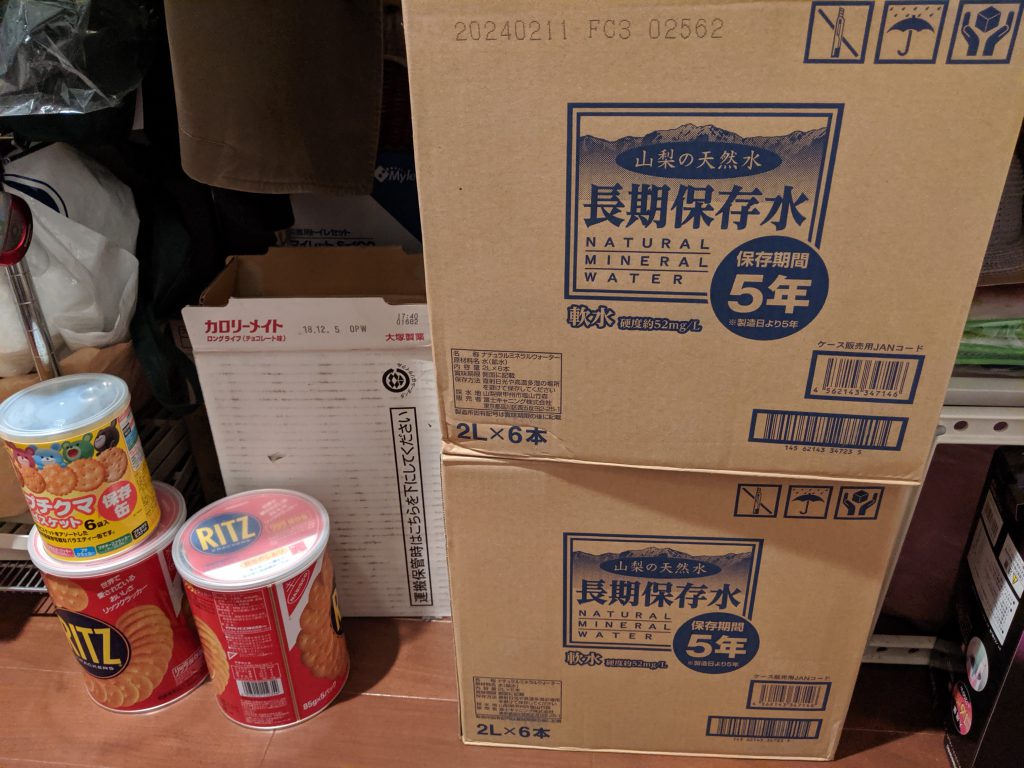2ヶ月分ですね。
まずは紙の本から。
続いて電子書籍。
以前、紙の本で持ってましたが読みたくなり再読。社会学よりのルポですね。個人に長い間インタビューを積み重ねていて、数年の間に人の境遇が動くのがなんというか臨場感ある。
USJ復活の立役者と目されている森岡茂さんの著作。マーケ本ではなく、なんというか人生訓みたいなかたちです。ただ、中身はなかなか壮絶。P&G時代にアメリカに赴任して、現地の人々とやりあって自分がどう思っていたか、ということは、苦しかったなんてもんじゃない、すさまじく壮絶、と言えるものだと思います。自分も苦しい時はここ読み返して、これに比べれば大したことないじゃんと思うようにしてます。
人口に関する新書です。人口減少はすでに始まり、ここから日本はどうなっていいくのか、というのはまことしやかに言われる昨今ですが、リアルな統計で見せられるとかなりダメージでかいですね。明るいことを思い浮かべるのは難しいような感じで。もう、こうなったら、ソフトパワーで乗り切って行くしかないと思うので、そこの割り切りができるかな、と思います。
佐藤優さんの新書。人生論みたいなものですね。自分も40代なのでどうなのか、と思い買いましたが、著者が50代で、それを踏まえて40代はどうだったか、ということが書かれていて実感を持って読めたかと思います。
これもキャリア論。著者の方は、リクルート出身ということでした。40代の転職について、良し悪しを事例を多く持って考察していました。これは参考程度ということで。

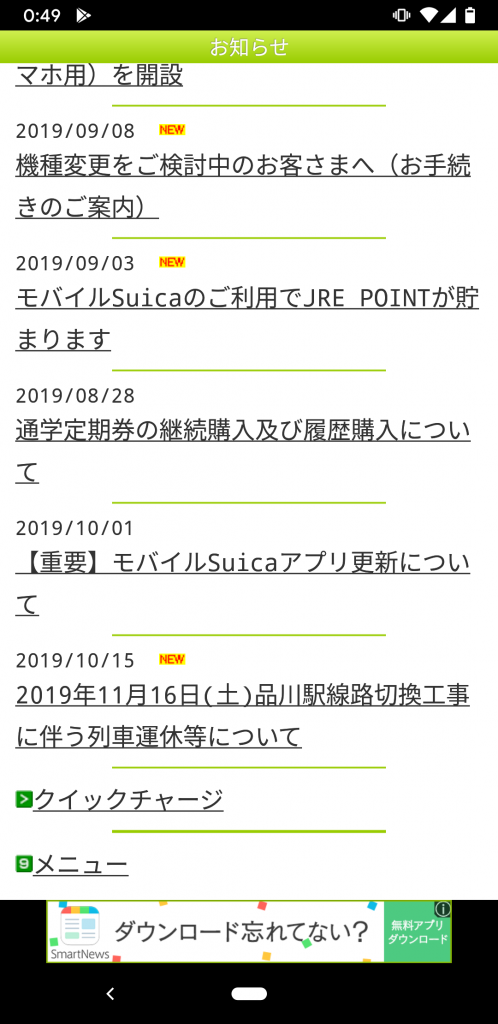
 左の白文字盤が2006年に買ったもの、左の黒文字盤は今年2019年に買ったものです。
左の白文字盤が2006年に買ったもの、左の黒文字盤は今年2019年に買ったものです。
 この白文字盤は、シチズンデザインというシリーズで数量限定で発売されてました。ヨドバシカメラで見かけて一目惚れして、何度も見に行っていい時計だな〜と思って、自分にしてはなかなかな金額でしたが思い切って買いました。定価は100,000円強くらいだったと思います。ただ、その後、このシチズンデザインも続いて製品はたしか出ず、この製品もそんなに人気あったような感じはしなかったので、あんまり売れなかったんじゃないかと思います。
この時計の特徴は、エコドライブ搭載、チタン製なので軽量、ということかと思います。デザインも主張しすぎず、復刻デザインながら素材やムーブメントは割と新進な感じでよいと思います。
この白文字盤は、シチズンデザインというシリーズで数量限定で発売されてました。ヨドバシカメラで見かけて一目惚れして、何度も見に行っていい時計だな〜と思って、自分にしてはなかなかな金額でしたが思い切って買いました。定価は100,000円強くらいだったと思います。ただ、その後、このシチズンデザインも続いて製品はたしか出ず、この製品もそんなに人気あったような感じはしなかったので、あんまり売れなかったんじゃないかと思います。
この時計の特徴は、エコドライブ搭載、チタン製なので軽量、ということかと思います。デザインも主張しすぎず、復刻デザインながら素材やムーブメントは割と新進な感じでよいと思います。
 横から見ると分かりますが、筐体の横がカーブして削り込まれていて、独特でかつ手にフィットする感じです。これは、元祖のチャレンジタイマーのデザインを踏襲しているようですね。
横から見ると分かりますが、筐体の横がカーブして削り込まれていて、独特でかつ手にフィットする感じです。これは、元祖のチャレンジタイマーのデザインを踏襲しているようですね。
 そして、黒文字盤の最新盤。
これはプロマスターというラインから発売されてます。シチズン100周年ということで、スペシャルキャンペーンが企画され、そこで復刻となったようですね。
そして、黒文字盤の最新盤。
これはプロマスターというラインから発売されてます。シチズン100周年ということで、スペシャルキャンペーンが企画され、そこで復刻となったようですね。
 横から見ると、やや大きくて大きさも重量もあるのが分かります。
なんか好きで揃えちゃってますね。まずは愛用し続けたいと思います。
横から見ると、やや大きくて大きさも重量もあるのが分かります。
なんか好きで揃えちゃってますね。まずは愛用し続けたいと思います。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/195040f0.30329409.195040f1.c8355220/?me_id=1209584&item_id=10435783&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F10keiya%2Fcabinet%2Fimg160001-161000-1%2F160178-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/195040f0.30329409.195040f1.c8355220/?me_id=1209584&item_id=10419997&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F10keiya%2Fcabinet%2Fimg143001-144000-1%2F143092-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F10keiya%2Fcabinet%2Fimg143001-144000-1%2F143092-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)